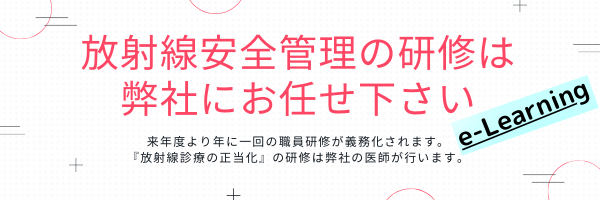ついに日本診療放射線技師会から
『診療用放射線の安全利用のための指針モデル』 なるものが公開されました。
以下にリンクを貼っておきます。
日本診療放射線技師会のホームページ
この指針で私が気になったのは、赤字 で示した部分です。
2)線量管理
医療放射線安全管理責任者は、放射線管理士 、放射線機器管理士等 と協働し、日本診療放射線技師会の「医療被ばくガイドライン(診断参考レベル DRLs2015の 公 表 を 受 け て )」(以下「医 療 被 ば く ガ イ ド ラ イ ン 」という。)、及び医療被ばく研究情報ネットワーク(Japan Network for Research and Information on Medical Exposures: J-RIME)が策定した診断参考レベル(以下「DRLs2015」という。)を活用して線量を評価し、診療目的や画質等に関しても十分に考慮した上で、最適化を定期的 に行う。
「最適化を定期的 に行う。」って、
ちょっと曖昧な表現な気がしました。
1年に1回程度でしょうか。それとも・・・
また、線量記録に関しても気になりました。赤字 の部分です。
医療放射線安全管理責任者は、放射線診療を受けた者の被ばく線量を、当該放射線診療を受けたものが特定できる形で被ばく線量管理システム を用いて記録する。※被ばく線量管理システムは、必須ではない。次に掲げるいずれかに記載することをもって線量記録としてもよい。
●医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 24 条に定める診療録
●歯科医師法(昭和 23 年法律第 202 号)第 23 条に定める診療録
●診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 28 条に定める照射録
●医療法施行規則第 20 条第 10 号に定めるエックス線写真
●医療法施行規則第 30 条の 23 第2項に定める診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用の帳簿
※ 自施設の方法を検討し、記載すること。
つまり、専用のシステムを使わない場合は、
カルテ
照射録
エックス線写真
RI使用の帳簿
これらに記録すること。
これって、PACS に記録もアリってことですよね?
いろんな学会で被ばく線量の記録方法について議論されていたみたいですが、
結局こうなりましたね。
記録と管理は分けて考えるところがミソですか。
さぁ、みなさん!!
やるべき研修の内容も明らかになったので、
そろそろ来年度に向けて準備を始めましょう!
具体的な線量管理の実務については、
私の理解がまとまり次第ブログで書かせていただきます。
それでは、今後もよろしくお願いします。
【ブログ】IVR装置の被ばく管理